
| 道しるべ・トップ/あらすじ |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| ■ 都会での準備篇 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| Chapter0. としのはじめの家族会議 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| Chapter1. プロローグ |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 1-1. 四度目の人生 |
| 1-2. 人生の四季、おりおりに |
| 1-3. フォースクオーターの岐路にたって |
| 1-4. わたしたちの時代 |
| 1-5. 望郷 |
| 1-6. 田舎でやりたいビジネスのかたち |
| 1-7. 将来設計計画書 |
| 1-8. 伊豆の温泉で |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| Chapter2. 2008年のできごと |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| Chapter3. 2009年のできごと |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| Appendix1.笹村あいらんど視察 |
| Appendix2.たんぽぽ堂視察の記 |
| Appendix3.すれ違いは埋まるのか |
| Appendix4.田舎の土地の探し方 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| ■ 移住開始篇 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| Chapter4. 2010年のできごと |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

Chapter1. プロローグ 〜心に沈殿していくもの、漠然の決意〜
プロローグ篇では、定住準備の具体的ものではなく、わたしたちの半生を眺望し、その気持ちが里山への定住に傾いていく過程や背景をひもときたいと考えています。
まずは、わたしがある日、啓示のように感じた人生観の話しから始めさせていただきます。
1-1. 四度目の人生
東京から、北へ北へと向かう急行列車にのりこんでみましょう。車窓には風景が流れていきます。町の家並みから山や川、あるいは田畑、そして海、また街並みや集落、といった具合に、その眺めは、少しずつ変化しながら、飽きることなく浮かんでは流れ、消えてきます。
それは、わたしたちの人生に似ています。昨日から今日、そして今日から明日。日々に流れていくわたしたちの生活は、日めくりのカレンダーをちぎるように、ほとんどは何の変哲もない平凡なできごとの繰り返しです。
しかし、列車の旅を大きな視点で俯瞰しますと、節目々々に明らかに変わっていく様が見てとれます。トンネルを抜けると雪国になることもあります。山あいをぬけて、忽然と拡がる海原に逢うこともあります。同じような海辺の景色でも、よく観察してみるとそれぞれにそれぞれの趣きがあることが分かります。
そういうことを自分の人生に置き換えてみますと、そういう節目がやはりあります。それが、わたしの場合、どうも18年周期であるようなのです。18歳のとき、36歳のころ、その前と後では、わたしの立っている位置や役割、生き方がたしかに違うのです。ターニングポイントとなっています。
18、36と来たのですから、当然、次を計算します。54歳。わたしの役職定年は55歳ですから、ちょうど重なります。そのあと、わたしにはもうワンクールが残っている、待っているのではないか、と思い至りました。40代のなかばを少し過ぎたころでした。ああ、俺はいま人生のサードクォーターにたっているのだ、と自覚したのです。
退職後を「第二の人生」と申します。余生と言われた時代もあります。これは、ちょっと違うのではないだろうか、と思います。いまの時代、50代なかばはまだまだ洟垂小僧のようなものです。ということは、その後のフォースクォーターは、まだまだ“なにかを為せる期間”なのではないだろうか。しかもそれは、サードの延長にある必要はなく、人生の集大成としての生き方をすることこそがふさわしいステージなのではないのか、という思いです。思いと言うよりも、『発見』に値する驚きです。これが、子会社や関連会社に下る、そういう先達や同じ境遇の多くの仲間とは違う歩みをしてみようかと考え始めたそもそものきっかけになります。わたしにとって、退職後は第4の人生なのです。
※フォースクォーターがファイナルかと言いますと、これは神のみぞ知るところになります。ですから、ファイナルクォーターという言い方は敢えてしません。70代中盤からの寿命があるならば、ご褒美の附録でとっておきます。そのときのテーマは「悠」、あるいは「遊」でしょうか。
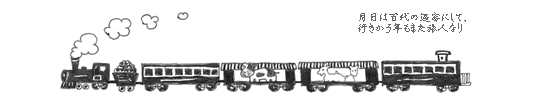
1-2. 人生の四季、おりおりに
誕生から18歳までのファーストクォーター。わたしは、秋田の大自然に囲まれて呑気に育ちました。昭和30年から40年代後半のことで、戦後の復興が東北のこの町にも轟きだした時代でした。物資には恵まれませんでしたが、こどもにとっては飽きることのない、遊びの場としての、あるいは学びの場としての山や川が手つかずで在りました。
あの頃といまのわたしとでは、住んでいる場所や環境も、一緒に暮らすひとも違います。あのころの持ち物がなにひとつ残っているわけでもありません。すべては消えてしまいました。ただ、その濃厚な体験が元素として、わたしという人間の根幹を構成しているような気がします。
わたしは音楽とスポーツと料理、というのは非常に似たところがあると思っています。すべては“残らない”のです。どんなに素晴らしい楽器の音色でも瞬時に消えていきます。スポーツのプレイも瞬間々々に消えてしまいます。料理も食べてしまいますと、なにも残りません。すべては無常、すべては移ろいという自然界の摂理にしたがっているかのようです。しかし、記憶や感動が残ります。消えてしまうものだけに、一層、記憶や感動が強烈に残り、こころのひだになって生まれ変わるような気がします。
いろいろな判断に岐路にたつとき、真贋を見極める眼がわたしにあるとしたら、こうやって、ただただ自然の中に育った、ということによります。そこには本物しかないからです。わたしの根っこは、ふるさとの自然にあります。
工業高校を卒業したわたしは、就職のため、親元を離れて都会に出ます。鎌倉の小さな営業所の配属でしたが、この会社にはありがたいことに社内大学の制度がありまして、入社4年目で合格。給料をいただきながら、エンジニアとしての基礎や応用をみっちり学ぶ機会に恵まれました。
25歳で結婚。三人のこどもを授かりました。
セカンドクォーターを季節にたとえれば、夏と言えるでしょう。ここを彩ったものは、仕事や家庭生活とともに、わたしの場合は“ラグビー”でした。仲間とともに泥んこで楕円球を追う日々がありました。わたしの選手としての才は凡庸です。体格に恵まれたわけではなく、むしろ小粒です。華麗なステップを踏むセンスがあるわけでもない。ただ、どういうわけか、キャプテンやコーチ、監督という役割を預かりました。
創部のころは、もうほんとうに負けっぱなしで、勝つのは不戦勝くらい。それが3年ほども続きました。ただ、練習の質や量では、決して妥協しませんでした。創設期の選手の入部動機は、そもそも良い汗をかいて、うまいビールを飲みたい、ことにつきます。したがって、春や夏の合宿には宴会気分で参り、夜中まで酒盛りです。そういう連中を朝6時にたたき起こして、ランパスなど、相当きついメニュをこなします。汚い話しで恐縮ですが、グランドの四隅にたぬきの糞溜のように吐しゃ物が溜まります。敵もさるものでして、あやつめ(わたしのことです)をもう少し酒で潰しておかないと練習がきつくてかなわぬ、ということになります。前夜を上回る宴会が始まります。翌朝6時には、また叩き起こして、きちんとメニュをこなします。3日もやると、こちらも相当まいってきますが、こうなったら意地の張り合い。ついにはやっこさんどもが、阿呆らしい、やめた、となってくれます。
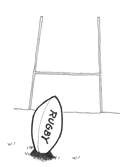 こんな具合でやってましたら、3年目の後半から、少しずつ勝てるようになってきたのです。そうなると会社も理解してくれ始め、大卒の経験者を採用してくれるようにもなる。既存の部員は、そういう若手に負けてなるものかと目の色を変えて、練習し始める。宴会中心ラグビー部が嘘にように変貌してきます。4部リーグからスタートしたチームが、わたしが監督最後になるシーズン、36歳のときには社会人リーグの1部まで昇格できたのです。
こんな具合でやってましたら、3年目の後半から、少しずつ勝てるようになってきたのです。そうなると会社も理解してくれ始め、大卒の経験者を採用してくれるようにもなる。既存の部員は、そういう若手に負けてなるものかと目の色を変えて、練習し始める。宴会中心ラグビー部が嘘にように変貌してきます。4部リーグからスタートしたチームが、わたしが監督最後になるシーズン、36歳のときには社会人リーグの1部まで昇格できたのです。
こういう風にお話しますと、いかにもリーダシップがあったように聞こえるかも知れませんが、そうではありませんで、個性派揃いのデコボコのメンバーが、ラグビーという競技を通じて、ひとつのチームをともどもに創りあげていったということです。わたしはその先頭を颯爽ときっていたわけではなく、牧羊犬のようにひたすら集団の中や周囲を走り回っていた感じでした。ただ、そういうチームだけに、ひとりひとりのチーム愛は深かったと思います。だから、いろいろな失敗も、成功体験も素直に全員で共有できたのです。
ラグビーというのは、体をぶつけ合うからなのでしょうか、人間と人間の密度が非常に濃くなるスポーツです。いまでも、当時のメンバーと集まるたびに、僕らの人生の一頁にラグビーがあるのとないのとでは、その景色が違うね、と言い合います。
ラグビーの季節を終えると、ビジネスマンとして、そして家庭人としての責任を果たす時代がやってきます。
冷戦の終結とともにグローバリゼーションが台頭し始め、各企業の海外進出に拍車がかかります。企業の生産等活動を支えるITシステムや通信回線の整備のため、海外でのビジネス展開が活発となりました。わたしは、そのチームに配属されて、世界中を飛び回ることになります。欧米やアジア諸国、中東など、30カ国を超える国々を訪れました。外国に行くことは、日本を知ることにつながります。自分がいかに「日本や日本人」を知らないでいるか、ということを痛感させられる機会になりました。
民間の製造業のユーザが圧倒的に多いのですが、某自動車がフランスのヴァランシエンヌという街郊外に工場をたてた2年越しのプロジェクトは、なにもない野原の状態から関わりましので、思い出に強く残っています。また国家的な大型プロジェクトのライフラインとなるシステム一式をまかせられたときの、しびれるような感覚はなんとも言えないものでした。ひとつひとつのプロジェクトにそれぞれの思い出と思い入れがあります。たしかにたいへんですが、一仕事をやり終えたときの達成感たるや、なんとも言い難いものがあります。
ここでも、最初の3年は試行錯誤の連続で、なかなかものになりませんでした。ただ、必死にくらいついて、10年もやってみると、いつのまにかなんでもござれになっている自分に気づきます。
こどもたちは、いまは27歳を筆頭に、25歳・23歳となりました。まだ所帯は持っていませんが、みな社会人として働いています。こちらもそろそろ巣立ち、そして子離れの時期となっています。わたしの55歳の役職定年と機をほぼひとつにして、家庭の内でも育つ者、育てる者の関係がいよいよ分胞し、独立した間柄になろうとしています。
1-3. フォースクォーターの岐路にたって
18年というこの周期や、それぞれのテーマは、わたしが意図して創り出したものではありません。そのときどきを一生懸命走ってきた、その成り行きによるものです。
ただ、人間、ひとつのことを3年やってみれば、そして10年続けられれば、ということを学ばせてくれました。
そしていま、フォースクォーターを前に、最後のこの期は、自分自身でテーマを持って臨んでみたいと思うようになっています。
しかし、それでは、そのテーマとはいったいなんなのだろう、わたしは何をすれば良いのだろう、そもそもわたしになにができるんだろう、ということになります。
さらに、思いを寄せてみると、そこには、わたしだけではなく、長く連れ添った妻がおります。
つまり、わたし“たち”はなにをすれば良いのだろう、そもそもわたし“たち”になにができるんだろう、ということになってくるわけです。
思い当たるのが『食』ということでありました。
わたしたちは、都市部に集団流入して青・壮年時代を過ごし、大量生産・大量消費・大量廃棄の生活様式に馴染みながらも、懐疑も抱き続けてきた世代です。その中、食の安心や安全について、子育てなどを通じて、共通の興味を持ち、いろいろな調理を楽しむまでに至りました。市民菜園で野菜を育て、調理も夫婦で分け合って行ってまいりました。出来合いの惣菜や冷凍食品などはもちろん、化学調味料等も拙宅には置いておりません。この数年、スローフードという言葉がメジャーになりましたが、かなり前から実践していたということになります。
その原点に、貧しかったが豊かだった食卓の記憶が濃厚にあります。高級でなくとも、野山や海から採れる食材を手間ひまかけて調理したものに囲まれた時代が、日本にもありました。
近頃、食品偽装などのニュースに触れるにつれ、憤りをとおり越して心が痛みます。『食』という生活の根源となるものをないがしろにする国や企業、あるいは国民には、手痛いしっぺ返しが待っているような気がします。安心で安全な食材をつくり、それをいとおしむ気持ちで調理すること、そこにある笑顔や語らい、そういうものを追求してみたい、そして提供してみたい、という強い気持ちがあります。
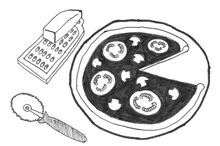 もう十年近くも前のことになりますが、イタリアのミラノに某商社のプロジェクトで出張したことがあります。その社長に連れ立って入ったリストランテの印象が強烈でした。高級でもなく、観光客が訪れるような洒落た店でもありません。料理も特に凝ったわけではなく、茹でたタコにルッコラ、トマトだけのパスタ、ポルチニ茸のソテー、・・・・、しかし、おそろしく美味い。ミラノにはパリから移動して入ったんですね。だから、パリで手のこんだフランス料理をしこたま喰べている。それを圧倒するものがありました。そして、みんな笑っているんですね。うまいものを食べ、ワインを飲み、マリーという給仕と世間話しをかわしながら、みんなが微笑んでいる。ああ、いいなぁ、料理というものは、こうやって笑顔をもたらすものなんだなあ、としみじみ感じました。『食』に対する姿勢の原点となっている出来事です。
もう十年近くも前のことになりますが、イタリアのミラノに某商社のプロジェクトで出張したことがあります。その社長に連れ立って入ったリストランテの印象が強烈でした。高級でもなく、観光客が訪れるような洒落た店でもありません。料理も特に凝ったわけではなく、茹でたタコにルッコラ、トマトだけのパスタ、ポルチニ茸のソテー、・・・・、しかし、おそろしく美味い。ミラノにはパリから移動して入ったんですね。だから、パリで手のこんだフランス料理をしこたま喰べている。それを圧倒するものがありました。そして、みんな笑っているんですね。うまいものを食べ、ワインを飲み、マリーという給仕と世間話しをかわしながら、みんなが微笑んでいる。ああ、いいなぁ、料理というものは、こうやって笑顔をもたらすものなんだなあ、としみじみ感じました。『食』に対する姿勢の原点となっている出来事です。
もうひとつは『共生』です。これはテーマと申しますか、生き方のベース音のようなものですが、いま現在のビジネス社会での『競争』から軸足をずらし、『共生』というものを基軸に置いた生き方をすべきだろうと考えております。勝った、負けた、の競争の社会は、実は非常に面白いのです。IT分野は、グローバリゼーションの先端を行くビジネスで、国と国との壁を乗り越えていきます。しかし、そういうビジネスに身を置きますと、同時にグローバリゼーションの陰にもいろいろ直面し、考えさせられることがあります。
1-4. わたしたちの時代
わたしたちが生きてきた時代を振り返って、そのキーワードを並べてみます。
(日本では)
・ 戦後の世代・・・・経済の急成長とあふれていく物資と情報
・ 若者の都市流入・・・親から子へ、子から孫へと受け継がれていけない時代
・ バブルの崩壊・・・豊かなのか貧しいのかわからない社会
(世界では)
・ 冷戦の終了・・・資本原理主義・競争至上主義の台頭
・ マネーゲーム、金融バブルの崩壊・・・行き過ぎた資本主義への暗雲
・ グローバリゼーション・・・地球規模での農経済の崩壊
競争市場主義に基づくグローバリゼーションは、各国の規制緩和など、開かれた世界への飛躍的な進展をもたらしました。また、経済の世界化に拍車がかかり、貧富の差が拡大することになりました。民族原理主義は、その反動・反作用として台頭してきたものと考えて良いと思います。
2001.9.11、セプテンバーイレブン、ですね。米国の同時多発テロ、そしてその報復としてのアフガン侵攻。そのころ、「もしも世界が100人の村ならば」が、インターネット上でまたたく間に世界中に広がりました
。
世界には63億人の人々がいますが、もしもそれを100人の村に縮小したらどうなるでしょう
・・・・(中略)
6人が全世界の富の59パーセントを所有し、その6人ともがアメリカ国籍
80人は標準以下の居住環境に住み
70人は文字が読めません
50人は栄養失調で苦しみ
ひとりが瀕死の状態にあり、ひとりは今、生まれようとしています
・・・・(後略)
非常に平易な文章ですが、いまの人類のありさまを表現しているものと思います。亡くなられた方を悼む気持ちは大事ですし、テロは決して許容してならない行為ですが、世界のかたちがいびつになっていて、その狭間での不幸な事件という見方をしますと、被害を受けた米国はもちろんですが、攻撃したとされる中東の集団にもまた、追いつめられた被害者の影が見えます。
もう少し身近な話題に変えましょう。日本の農の惨状というのも、戦後の工業立国日本、あるいは牛肉・オレンジに始まった食材の貿易自由化による負の面です。農作物のコスト構造は、工業製品とは違い、人件費や土地代などの占有率がいかんともしがたく高い。したがって、中国などから低い関税で野菜が入り込んでくるとひとたまりもありません。減反や高齢化、作っても手間賃にもならない取引額。そういう世界になっています。
それでは、中国の農民がその分、豊かになっているのでしょうか。それがぜんぜん違うのです。彼らは、日本に輸出する作物をつくって、自分が食べるものには窮しているんですね。日本の農民も中国の農民も追い詰められている、そんな馬鹿なことが実際に進んでいるのです。
これは、本来『共生』の領域にあった農生産を、経済至上主義が『競争』の世界に引きずり込んだことによって起きている事象なのではないでしょうか。農業という実直な青年が、老獪・狡猾な商売人たちの中でもみくちゃに翻弄されているように見えます。
食料自給率等に注目し、日本の農の将来を憂う声があがっています。次世代の農のなり手がいなくなれば、この国から農産業が消えます。農家を救え、というわけです。
これ、おかしいと思いませんか。農家が消えて困るのは、農家を救えと叫ぶ都市生活者その人です。農家の人は、高齢になろうが、自分で食うものくらいは自分の畑でできます。ひとさまの口に入れるものまでは、もうつくりません、ということはあるでしょうが。
そうなれば、そしてもし、他国のなんらかの事情で、輸入にとどこおりが生じますと、日本人は、とくに消費社会にある都市生活者はたちまち干上がります。農家を救え、と高所から言っている場合ではないのです。
わたしたちの生命の源泉である「環境」や「食」に関する危機感が声だかになりながらも、多くは外野席に座って、政治家や行政の悪口だけを言っているように見えます。大画面の液晶テレビを買い、高機能の携帯電話やiPodを操り、昼食にマックをほおばり、カップラーメンをすする、そういう国民ばかりになっていけば、この日本という国は間違いなく潰れます。政治や行政の次元以前、国民の無知性の問題です。
安心で安全で、品質の高い食材には、きちんとした対価を支払うべきですし、そういう生産者に利益を還元できる仕組みが必要です。
ビジネス社会に30数年間身をおいて、ひたむきに走ってきたわりには、省みますとこの国は良くなっていないなぁ、という思いがします。子々孫々に胸を張って伝えられるものがないのならば、それはわたしの、あるいはわたしたちの世代のひとつの罪です。すくなくとも同世代1,500万人分の1の責任が、わたしにある、と思っています。
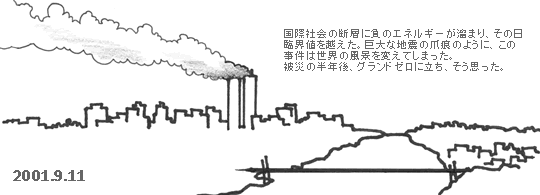
1-5. 望郷
時局講演めいたことから、わたしの田舎定住のことに戻りましょう。
フォースクォーターのテーマは、いずれこうして『食』と『共生』というキーワードで定まりそうです。それでは、なぜ「田舎」なのでしょうか。都市部、もしくはその周辺部でもやりようによってはいくつもやり方はある筈です。
いずれは田舎に移り住みたいという想いが、40代なかばのころからあったことは、既に述べたとおりです。そういう気分があった、というだけで十分な動機と思いますが、しいて挙げるとなる次の3点が理由めいたものになります。
ひとつは±0ismです。
静岡県立静岡がんセンタで院長をつとめておられる鳶巣賢一さんという方がいらっしゃいます。わたしが会社に入り、藤沢は鵠沼の独身寮に住んでいるときに、京都大学卒のキャリア組として入社、わたしの向かい部屋に入寮されました。まったくわけへだてなく人とおつきあいするエリート臭のない方で、わたしも随分可愛がられました。大酒飲みで、部屋で一升瓶を傾けながら、大いに語り、またいろいろなことを教えてもらいました。
おれは医者になることにした、と入社1年でそそくさと辞職。廃品回収などのバイトで生計をつなぎながら、翌年、見事に京大医学部に合格されました。
仏教哲学と申しますか、そういうことも良く話されました。
人間、オギャーと裸で生まれて、やがて裸に戻って土に還っていく、それだけのこと。悠久の過去と永遠の未来のなかで、人間の生が点のようにある。人生の途中々々で右や左、上や下があっても、人生の総和はとどのつまり±0になっているらしい。
ひとりものが結婚した家庭に行くと、うらやましいと思う。ところが、いざ所帯をもってみると失ったものに気づく。ヒラ社員は役職づきの上司の姿に憧れる。しかし、実際そうなってみると、立場で行動しなければならない窮屈さを感じる。
得たものがあれば、失うものがある。なにかをなくしたと思えば、なにかを得る。失ったときに嘆かず、得たものに有頂天にならないことではないか。所詮、人生はプラスマイナスゼロなのだから、とたしかそういうようなことでありました。
思春期の体験、その時期になにをやって、なにを考えたか、というのは非常に重要です。わたしのその後のもろもろの判断のいしずえは、このころに育てられたのではないかと思えています。
さて、わたしたち夫婦はファーストクォーターを田舎で過ごし、セカンドとサードを都会で生活しました。ですから、フォース以降は田舎に棲めば、フィフティフィフティになります。わたしたちの人生にリトマス試験紙を浸ければ、総和として中和となります。こじつけのようなことに思われるかも知れませんが、中庸であることは実に難しく、しかし大切なことです。そのためには、生きる環境が中庸であるように意識しなければならないような気がします。
ふたつめはきわめて心情的なものです。原風景への回帰、つまりは望郷の念です。
人間の記憶というのは、たいへんおもしろいもので、五十路のころから、昨晩食べたごはんのおかずを思い出せないのに、幼いころに見た風景などが忽然と浮かび上がったり、夢にでてきたりすることがあります。
 あのアキアカネの大集団はなんだったのでしょうか。毎年秋口に入る数日間、実家近くの神社の小山に、空や山までも埋め尽くすように赤とんぼがやってきました。自転車で坂道を疾走すると、よけ切れない赤トンボが、体や顔にぱちぱちと当たります。突然、そういう記憶が甦ってくるのです。
あのアキアカネの大集団はなんだったのでしょうか。毎年秋口に入る数日間、実家近くの神社の小山に、空や山までも埋め尽くすように赤とんぼがやってきました。自転車で坂道を疾走すると、よけ切れない赤トンボが、体や顔にぱちぱちと当たります。突然、そういう記憶が甦ってくるのです。
オニヤンマやオオシオカラ、キアゲハなどを追った夏の山や池。
わたしは高校時代、新聞配達をしていましたが、真冬の朝日が昇ってくる時間は、白馬寺というお寺にちょうど配達するタイミングでした。雪景色の向こうから、松林をぬって朝陽が差し込んできて、きまって雉が鳴くんです、ケーン、ケーン。敬虔な気持ちになりますね。
そういうことが思い出されるのです。そのとき、ああ、還ろうかな、と思うのです。
ですから、これは理屈ではなく、わたしの奥底から湧き上がってくる感情です。
ふたつめ・・・と申しましたが、これが源なのでしょう。心の底の扉を小さくノックするものがあり、その声を聞いてみるところから、すべては始まりました。こつんこつんというノックは、ノスタルジーそのものだったかも知れません。扉をあけてみると、そこに人生観や価値観というものがあったり、それをちょっとめくってみると『食』や『共生』というテーマが転がっていたりする、ということなのでしょう。
わたしは秋田市の、妻は五所川原市の出身ですが、幸い双方とも両親が健在でおります。
みっつめの思いは、人の道、というのでしょうか、遠く離れて親孝行ひとつして来ませんでしたので、最後はもう少しそばにいてあげたいということです。
親子関係は、スープの冷めない距離が理想、と申します。それよりは少し遠くなりますが、秋田と五所川原のまんなかを取ると白神山地のあたりになります。定住の場所探しは、いつのまにか秋田県の北部に絞られました。あまり意識はしていないつもりでしたが、知らず知らずの間にそういう心理が働いたのかも知れません。
郷愁を満たすのであれば、わたしの故郷の秋田市へUターンというのが、普通のシナリオとなるでしょうが、その考えはありませんでした。Uターンとは、わたしだけにとってUであって、夫婦でフィフティの関係とは言えません。お互いを足しあいながら、一緒になってなにかを創っていく、わたしたちはいままでそういうことでやってきましたので、それはこれからも踏襲するものだと想っています。
わたしたちにとって、秋田への定住は、田舎の人に戻ることではなく、また、都会を忌避し、その生活をすっかり捨てることでもありません。田舎で生まれ育って、長く都市生活を経験した者が、その先にある新しいライフスタイルを創出していくスパイラルリターンであるような気がします。
1-6. 田舎でやりたいビジネスのかたち
わたしが商売について語るのは、その道の方には笑止に値することと思いますが、スパイラルリターンのさきにあるものとして、やってみたいイメージがあります。
かつて厳冬の釧路湿原に丹頂を追ったことがあります。阿寒町や鶴居村をいくどとなく訪ね歩きました。当時の鶴居は辺境の集落で、日に数本のバスしかありません。観光客にこびるところもなく、好きでした。
その日の鶴の行動を観て、採餌場で待ち受けたり、湿原に入ったりします。
餌場には、粗末な掘建て小屋がありました。幹道からちょっと外れたそこにポツネンと居ると、面白いことに、日に何人かは、かならずやって来て、声をかけてくるのです。氷点下20℃を超える厳寒、釧路の街から1時間以上もかかり、喫茶店などありもしません。そういうところに、ときに遠く九州からも人が訪ねてきます。わたし同様に機材をかついだアマチュアのカメラマン、旅行のついでに寄った風情のご夫妻、タクシーでかけつける友人どうしのグループなどなど。
この季節に、こんな場所まで鶴を目当てにやって来るようなわたし自身を、わたしはそうとうの酔狂者と思っていました。たしかにマジョリティにはなりうべくもありませんが、でも、独りでもなかった、ということです。丹頂に魅力を感じて、わざわざ足を運んでくるひとはひと握りなのかも知れませんが、確実にわたし以外にも居る、ということなのです。その場に居合わせた者同士、言葉をかわし、なんらかの共感を得ていく、これは、結構、素敵なことでした。
もし、わたしたちが、もっとも満足と思える生活を創ることができたならば、そしてその空間の一部を切り取って、リストランテというかたちで提供できるのならば、それを快適と感じていただけるひとは確実に居るのではないか。
かつての鶴居村の掘建て小屋のように、大多数のひとびとには、その存在すら分からないものでも、そこに琴線の響きをみいだす一群もあるのではないか。
そういう思いがあります。
わたしが開きたい店は、そういう小さな素数のようなものであり、それが市場の最大公約数を求める開業論理にたがっても構わないではないか、と考えている理由です。
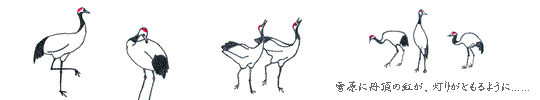
1-7. 将来設計申告書
わたしたちの会社では、管理者になりますと、かぞえで齢50になる年から「将来設計申告書」を提出します。いつまで在籍したいか、その後はどうするのか、斡旋を受けて子会社などに向うか、自営、もしくは自活するのか、という意思表示をする場です。多くの大手日系企業になんらかのかたちで残っている制度です。
人生七十古来稀なり、の時代はとまれ、長寿・少子化の現代に見合った雇用のあり方が本来ある筈です。労働資産という観点からも社会的損失と言えるのではないかと思えます。
ただ、わたし個人となりますと潔く身をひきたいと考えています。いまのわたし自身の地位は、かつての先輩達がその道を譲ってくれたがためにあることを思い起こすと、そうなります。今度はわたしが後進にそのバトンを渡すときです。
また、長寿の時代であればこそ、ここで次の生き方を考えてみる機会を与えられたとポジティブに受け止めるべきです。もしこういうものがなければ、わたしの場合もこのまま60歳、あるいは65歳と行き着くところまで会社員であり続けた気がします。ところが、いまは年金生活に入れたから、悠々自適で豊かな老後を満喫できる時代ではありません。65歳になったけれど、まだまだ仕事が生きがいでワクワクしている、そういう人生設計図があっても良いのではないでしょうか。
さて、わたしはこの「将来設計申告書」には終始一貫として、定年後は秋田に戻って自活する旨を記載し、報告をしてきました。なにか準備をしているわけでも、確たる信念があるわけでもありませんが、なんとなく、というよりは、もう少し深いところから「感じる」ものがあったのだと思います。躊躇することなく、そう書き続けてきました。
こうしてみますと、田舎への定住準備の活動歴はこの一年程度ですが、深層でのアイドリングは、かなり前から始めていたということなのかも知れません。
1-8. 伊豆の温泉で
将来設計申告書の件は、いちども妻には相談せず、独断で出しておりました。ですが、おりおりの会話でとっくに見通されており、2006-7年ころには、定年後は秋田に定住しようね、という了解が夫婦間でできていましたし、子どもたちにも、還るよ、という意思だけは伝えていました。とは言え、肝心なわたし自身の構想がはっきりしていないこともあって、きちんと向かい合って話すまでには至っていません。とくにパートナーとなる妻は、それを待っていたのだと思いますが、意気地がないものでわたしの方で先送りにして避けていた、というのが真相です。
仕事にかまけて、家庭の大事をおろそかにしてしまう愚を、男達は犯し、のちに悔いるものです。
妻は小学生のころから剣道を続け、子育て期に10年ほどのブランクがありましたが、現在も町の道場に通い、あるいは近所の中学校で格技指導協力講師としての活動も行っております。その仲間とは家族ぐるみのつきあいをしており、ホームパーティに招きあったり、ときには一緒に旅行に出かけたりします。2007年11月のこと、この3組の夫婦での中伊豆への温泉旅行がありました。
その場で妻の友人から指摘されました。あなたは身勝手に見える、いまのままでは彼女が可愛そうだ。
反省しましたね、まったくそのとおりですから。
それではと、自分の考えをかいつまんで述べてみようとしましたが、頭や心が整理されておりませんので、支離滅裂になっていくのが自分でも分かります。情けないほどに、これではまずいと感じました。
 年が明けたら、秋田に行ってみよう、四季ごとに訪ね、そろそろ準備をはじめてみようという心づもりをしていました。行ってみれば、ただなんとなく動き出すとたかをくくっていたところがあったのでしょう。思い出の抽斗(ひきだし)にある故郷の地を、これからの生活の場所としてかえていくのは雑作のないことだという郷里への甘えがあったのかも知れません。しかし、わたしたちのことを良く知っている友人にさえ、しどろもどろで説明できないのであれば、なにひとつ動かすことができません。
年が明けたら、秋田に行ってみよう、四季ごとに訪ね、そろそろ準備をはじめてみようという心づもりをしていました。行ってみれば、ただなんとなく動き出すとたかをくくっていたところがあったのでしょう。思い出の抽斗(ひきだし)にある故郷の地を、これからの生活の場所としてかえていくのは雑作のないことだという郷里への甘えがあったのかも知れません。しかし、わたしたちのことを良く知っている友人にさえ、しどろもどろで説明できないのであれば、なにひとつ動かすことができません。
あの中伊豆でのひとことは、大切な気づきをもたらせてくれました。深謝。
わたしのなかにスイッチが入った瞬間でもありました。


