








<初稿2007.4.17>
そのとき僕らははたちを過ぎたばかりで、場末の呑み屋で無邪気に盛りあがっていた。
藤沢市に“小鳥のまち”という通りがあった。戦前、その一画には遊郭が並んでいたそうだ。うらぶれて怪しげな雰囲気に惹かれて、さ迷うように飲み歩いた。
宮崎、山口、長野、山梨、そして僕が秋田。高校を出て就職し、独身寮で出会った仲間だった。親もとを離れた解放感と、とどのつまりはさみしかったのだろう。それを埋め合うかのように、僕らはつるんで飲み歩いた。
僕はその寮を一年余りで出て、アパートを借りた。大学に行こう、そのために勉強しようと考えたからだ。そのことは誰にもあかさなかったが、薄々感じるものがあったのだろう、誰もアパートを訪ねてこなかったし、僕も寄せつけようとしなかった。それでも、遅々として進んでいかない受験勉強に行き詰っては、僕は仲間を誘い、あるいは誘われて、その焦燥を打ち消してしまうかのように飲み歩いた。
たわいもない冗談ばかりが飛び交い、誰も心の底の孤独を口にしなかった。しかし、みな、きっと知っていた。
十年経ったら、また逢おう、ここで再会しよう、と唐突に誰かが言い出した。十年後の今日今夜、ここに集まろう。僕らの道が早晩に枝別れし、バラバラになっていくことも知っていた。
そのころ、十年後とは、遠い未来であった。そして、未来とは輝かしく、自ずと拓かれていくべきものであった。そうだ、また逢おう、ここで逢おう。僕らは、その記憶を押し込めるかのように、コースターの裏に約束の日にちを書き、それぞれのポケットにしまった。みな、その約束が果たされることはないだろうことを知っていた。
やがて、ひとりふたりと藤沢の町を離れて行った。田舎に還った者もいたし、会社を辞めた者、結婚した者もいた。僕もやがて東京に出た。
あの日のコースターのゆくえは知れない。十年後の今日今夜も、とうの昔に過ぎていった。そんな約束があったことすら、きれいに忘れてしまっていた。淡い豆電球のフィラメントが、人知れず切れたまま放置されたようなものだ。
だが、あれは友情であったのだと思う。高度成長期の大都市への人口流入の時代だった。田舎暮らしから都市生活へ、高校生から社会人へという環境の激変、それを経験した者は、私達の世代にはごまんといる。無邪気な集団は、古里の川から大海に流された稚魚のほんの小さな一群(ひとむれ)だった。
独り立ちできずにいる集団がもたれあいながら生きていた。
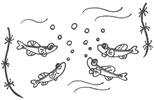 だが、それでも僕は、あれはたしかに友情なのだと思う。いつかは大陸棚をひとりで離れていく日か来ることを、僕らは知っていた。そして、一匹、また一匹とそのようにしたのだった。それは挑戦だったのかも知れないし、逃避だったのか知れない。毅然として向かっていった者もあれば、挫折して出て行った者もある。しかし、誰しもが懸命にもがきながら生きていたことは、たしかであった。そのもがきのなかで、触れ合いがあったということなのだ。
だが、それでも僕は、あれはたしかに友情なのだと思う。いつかは大陸棚をひとりで離れていく日か来ることを、僕らは知っていた。そして、一匹、また一匹とそのようにしたのだった。それは挑戦だったのかも知れないし、逃避だったのか知れない。毅然として向かっていった者もあれば、挫折して出て行った者もある。しかし、誰しもが懸命にもがきながら生きていたことは、たしかであった。そのもがきのなかで、触れ合いがあったということなのだ。
あのときの仲間と、もしまた逢うことがあるならば、やはり場末の呑み屋が良い。肩を並べて、焼酎を飲みながら、きっと冗談だけが飛び交うのだろう。それでも、よう頑張ったねえと、それにしてもお互い歳をとったもんだねえと、心のそこの言葉もひとつやふたつは吐くだろう。それで十分である。
