








<2007.04.10>
基地のファーストゲートから目的地までは、砂の海を裂いて続く一本道を、ジープを駆っても、まだ二十分余りかかる。道の両脇には、夥しい数の高射砲や装甲車の残骸が、湾岸戦争当時の黒焦げのままに放置されている。今朝は空が壊れたかのようだ。強い雨に混じり、稲妻が光る。雷は、この平伏な砂漠のなにを標的にして落ちるのだろうか。そんなことを考えると、車の中は安全と聞くが、外気は50℃近いというのに薄ら寒くなる。このまま走り続ければ、ほどなくイラク国境に通じる、そういうところに米軍のクウェート・キャンプヴァージニアがあり、その一画に自衛隊の天幕が連なっている。
その頃、わたしは防衛庁イラク平和復興支援活動に伴う通信システムに関わるプロジェクトマネージャの任にあった。
駐屯も三年目となり、いよいよ陸上自衛隊の撤収が決まった。サマワ本隊をHubとし、スター状に四箇所の拠点を衛星ネットワークで構成している。キャンプヴァージニアは、そのひとつである。これだけの部隊規模の撤収には、通信設備も単純に撤去するだけというわけにはいかない。撤収支援本隊をクウェートに新設し、そこにHubを移設して、段階的に逓減する。撤去計画、後送・再用計画、新規調達計画、切替・試験手順、そしてContingency Plan。計画を練っていくにつれ、断崖絶壁の吊り橋を渡っているような気分になる。失敗の二文字は、もちろんあってはならない。
クウェートは、これで五度目の入国だ。現地の自衛隊スタッフと綿密な打合せを行うことが、今回の目的である。意識合せに一点の曇りがあっても、致命傷になりかねない。
長いプロジェクトになった。イラクには通信インフラもない、ベンダーもいない、われわれ、民間人が立ち入ることもできない、そういう環境にどうやって、6m級の衛星アンテナや10基を超えるラック規模のシステムを構築するのか。どうやって、保守・運用していくのか。通信は、人命を支えるライフラインのひとつである。絶対的に信頼できるものでなければならない。
通信隊員を教育し、彼らに現地ベンダーのミッションを担ってもらうことにした。それしか選択の余地がなかった。隊員は、三ヶ月単位で交代する。従って、教育もダウンサイズした実機を用意して、その期間ごとに派遣部隊を追いかけるようにして行った。まさしく官民協業。多くのメンバーの熱意と責任感に支えられ、ここまで概ね順調に運営してきたのだ。最後の最後に汚点をつけたくない。
自衛隊スタッフとの打合せは、白熱の中にもつつがなく終わった。かれらもさすがに良く考えてくれている。テゴタエ、アリ。ただ、本番はこれらからだ。一気に駆け抜けよう。
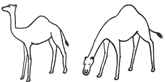 ホテルへの帰路、夕闇が迫ってくる。いつのまにか天候は回復し、西の空が赤く染まっている。遠くに石油プラントが見える。乾燥のせいだろうか、砂漠の国の夜景は美しい。プラント工場の灯火が幾百となくチラチラ光っている。緊張が解け、少し眠くなってきた。
ホテルへの帰路、夕闇が迫ってくる。いつのまにか天候は回復し、西の空が赤く染まっている。遠くに石油プラントが見える。乾燥のせいだろうか、砂漠の国の夜景は美しい。プラント工場の灯火が幾百となくチラチラ光っている。緊張が解け、少し眠くなってきた。
このプロジェクトを通じて、いろいろなことを考えさせられた。
国とは、民族とは、宗教とは何なのだろう。イスラムの民は信仰心に厚い。しかし、神と神が争うとき、人々の血が流れる。国と国との利権がからんで、戦争へと突き進む。そして、自衛隊の出動。
日本という国はどこに向かっているのだろう。わたしたちはなにをすれば良いのだろう。
眼を閉じると、灯火の残像が瞬いている。それは、幼い日にみた、夏の夜の蛍に想えた。
