








亙2009.7.17亜
偐偮偰丄儔僌價乕晹偺屻攜偑丄庒偔偟偰攛偑傫偱惱偭偨丅傑偩27嵨偩偭偨丅傢偐偭偨偲偒偵偼傕偆庤抶傟偱丄庒偄暘偩偗偁偭偲偄偆娫偩偭偨丅晽偺傛偆偵嬱偗敳偗偰偄偭偨丅
傢偨偟偼丄僠乕儉偺憪暘偗帪戙偺慖庤偱偁傝丄斵丄Ng偼曗嫮慖庤偺戞嘥婜惗偩偭偨丅
摉帪丄庡彨傪偮傔偰偄偨傢偨偟偼丄偁傞擔丄儔僌價乕晹挿偵屇偽傟偨丅晹壆偵擖傞偲丄娔撀偺偲側傝偵丄僽儗僓乕傪拝偨傆偨傝偺妛惗偑嬞挘偟偨柺帩偪偱嵗偭偰偄傞丅乬棃弔丄擖幮偡傞傆偨傝偩丄偟偭偐傝柺搢傒傠乭偲尵傢傟偨丅
惛湜側柺峔偊傪傒偰丄怱偑桇偭偨丅偙傟偱堦曕丄摜傒弌偣傞偧丄偲巚偭偨丅
傑偭偨偔偺庛彫僠乕儉偩偭偨偑丄偦傟偱傕抧摴偵楙廗傗崌廻傪廳偹傞偆偪偵丄彮偟偢偮偩偑彑偪傪廍偊傞傛偆偵側偭偰偄偨丅傗傟偽偦傟偩偗偺傕偺偑娨偭偰偔傞丄偲偄偆帺怣傕晹堳偨偪偵夎惗偊偰偒偨偙傠偩偭偨丅娤偰偔傟偰偄偨偺偩傠偆丅曗嫮嶔傪懪偮偵偼丄傑偝偵愨柇偺僞僀儈儞僌偵巚偊偨丅
恖偵懳偟偰傕丄慻怐偵懳偟偰傕丄愭峴搳帒偼戝愗偩偲巚偆丅
彑偮偨傔偵偼丄椙偄慖庤偑偄側偗傟偽側傜側偄丅偩偑丄椙偄慖庤傪屇傇偨傔偵偼丄寢壥傪弌偟偰偄側偗傟偽側傜側偄丅寋偑愭偐丄棏偑愭偐丄偺榑媍偵惓夝偼側偄偑丄揔愗側僞僀儈儞僌偱揔愗側搳帒偑堊偝傟偰偙偦丄暔帠偼僑儘儕偲摦偔丅屻偵暦偄偨偙偲偩偑丄偙偺偲偒偺曗嫮嵦梡偵傕丄夛幮撪偱偼巀斲椉榑偑姫偒婲偙偭偨傛偆偩丅愑擟偼壌偑偲傞丄偲偄偆晹挿偺傂偲偙偲偱寛傑偭偨丅
塸抐傪壓偟偨乬娍乮偍偲偙乯乭偑偄偨丄偲偄偆偙偲偩丅
擔杮幮夛偺曄摦偵偮傟偰丄偁傟偐傜傢偨偟偺夛幮偺宱塩宍懺傕偍偍偒偔曄杄偟偨丅偦偺攇傪偐偄偔偖傝側偑傜傕丄偲偒偳偒偺屻攜偵堷偒宲偑傟偰丄偄傑傕僠乕儉偑懚懕丒敪揥偟偰偄傞丅
徚柵偟丄夝嶶偟偨儔僀僶儖僠乕儉傕懡偄側偐丄屻攜偨偪偑丄傛傝嫮偔側傞柧擔傪栚巜偟偰婃挘偭偰偔傟偰偄傞偙偲偼丄側偵傛傝偺曮暔偱偁傞丅
傆偨傝偺怴恖偼婜懸偳偍傝偺妶桇傪傒偣偰偔傟偨丅側偵傛傝傕僠乕儉偵撻愼傒丄愭攜偐傜壜垽偑傜傟偨丅僾儗僀柺偱偼儊儞僶乕傪尅堷偟偨丅
桪傟偨慖庤偑棃偨悢偩偗丄帋崌偵弌傜傟側偔側傞儊儞僶乕偑弌傞丅偦偺恖娫偑晠偭偰偟傑偆偲丄傓偟傠懝幐偵側傞丅儕乕僟偲偟偰僠乕儉傪尅堷偡傞幰偵偼丄巊柦姶偲偄偆椘偑偁傞丅偟偐偟丄掙曈偱巟偊傞慖庤偨偪偑丄儌僠儀乕僔儑儞傪堐帩偟懕偗傞偙偲偼傎傫偲偆偵擄偟偄偙偲偩偲巚偆丅側偵傛傝傕婐偟偔丄偦偟偰屩傟傞偙偲偼丄曗嫮偑擭乆懕偔傛偆側偭偰埲崀傕丄偨偩傂偲傝扙棊幰偑弌側偐偭偨偙偲偩丅憂惗婜偺儊儞僶乕偼丄扤傛傝傕僠乕儉傊偺垽拝怱偑嫮偄丅傒側丄儔僌價乕偑岲偒偩偭偨丅偩偐傜丄帺慠丄帺暘偺偙偲傛傝傕僠乕儉傪桪愭偟偨丅偦傟偵偟偰傕丄婬桳側偙偲偩傠偆丅
偦偆偄偆僪儔儅偺傛偆側幚榖偺嵟拞偵丄傢偨偟帺怣偺惵弔偑偁偭偨偙偲偼丄峫偊偰傒傟偽丄恎偑恔偊傞傎偳岾塣偲尵偊傞丅
摉帪偺怴恖偺偐偨傢傟偱偁傞Is偼丄偄傑屘嫿偺嶳岥偱曢傜偟偰偄傞丅偳偆偟偰傕屘嫿偵栠傝偨偄丄偲偄偆堦怱偱丄悢擭慜丄夛幮傪帿傔偰丄墱偝傫偲傑偩妛惗偺巕偳傕偨偪傪搒夛偵巆偟偰丄扨恎偱娨偭偨丅岾偄嵞廇怑傕寛傑傝丄尦婥偱傗偭偰偄傞丄偲偄偆曋傝偑偁偭偨丅
嶐擭偺6寧丄弌挘偵偐偙偮偗偰丄媣乆偵嵞夛偟偨丅惀旕丄幚壠偵攽傑偭偰傎偟偄偲偄偆尵梩偵娒偊傞偙偲偵偟偨丅壠偺棤庤偵揷傫傏偑偁傝丄帺暘偱傗偭偨丄偲偄偆憗昪偑怉傢偭偰偄偨丅恊晝偝傫偺怉晅偗偼丄惍慠偲偟偰弉楙傪姶偠偝偣傞丅斵偺傕偺偼幹峴偟偰偄偨丅偦傟偱傕丄偦偺揷傫傏傪斺業偡傞斵偺昞忣偵偼丄偐偮偰懭墌媴傪捛偭偨惵擭偺柺塭偑偁偭偨丅栭偵偼丄儂僞儖偑壠傪庢傝埻傓偐偺傛偆偵晳偭偨丅偙傟偱傕丄彮側偔側偭偨傕傫偩丄偲偼傗偔傕斢庌偱傎傠悓偄偺恊晝偝傫偑欔偄偨丅
屘嫿偵娨傝偨偄丄偲憡択偝傟偨偲偒丄傢偨偟偼丄傗傔偰偍偗丄偲桜偟偨丅壠懓偼偳偆偡傞傫偩丄偲愢嫵傔偄偨偙偲傕尵偭偨丅
壌偑捫偗偨偁傫偢庰偱偡傛丄偲傆傞傑傢傟偨丅崄傝偑岥偄偭傁偄偵傂傠偑傞丅
傢偑傑傑側偙偲偼暘偐偭偰偄傑偡丄偱傕丄偳偆偟偰傕娨傝偨偄傫偱偡傛丄恊晝傗偍傆偔傠偑傑偩尦婥側偆偪偵丒丒丒偲懯乆偭巕偺傛偆偵榖偡岥傇傝偵梙偓側偄傕偺傪姶偠偨偙偲傪巚偄弌偟偨丅
偁偄偮丄棃擭偱23夞婖偱偡偹丅
偦偆偄偆榖戣偵側偭偨丅偦偆偩丄傕偆偦傟偩偗偺嵨寧偑宱偮丅
峴偭偰傗傜側偒傖側傜側偄傫偱偡偗偳偹丄嶥杫偼墦偄偟丄偦偆偄偆嬥傕側偄偟丄偤傂峴偭偰傗偭偰偔偩偝偄丄偍婅偄偟傑偡丅嫃廧傑偄傪偨偩偟丄Is偼儁僐儞偲摢傪壓偘偨丅Ng偺僌儗乕僩僨儞偺傛偆側晽杄偑巚偄偩偝傟偨丅
Is偼丄傢偨偟偲摨偠CTB偲偄偆億僕僔儑儞偩偭偨丅弐晀惈傗僷僗儚乕僋傪媮傔傜傟傞丅挿廈恖傜偟偄戦偺傛偆偵愗傟挿偺栚偮偒傪偟偰偄偨丅堦曽丄Ng偼丄儘僢僋偲偄偆僼僅儚乕僪偺拞妀偲側傞億僕僔儑儞偱丄傾僗儕乕僩偲偟偰偺憤崌椡丄摿偵撍攋椡傗僕儍儞僾椡偑昁梫偲側傞丅挿恎丄嬝擏幙偱丄將偺僌儗乕僩僨儞傪渇渋偝偣偨丅偙傢偍傕偰偱丄堦尒丄嬤婑傝擄偄偑丄栚偑偮傇傜偱壜垽偝偑偁傞丄偦偆偄偆偲偙傠傕帡偰偄偨丅
儔僌價乕偼丄懱偲懱傪傇偮偗崌偆僗億乕僣偱偁傞丅楙廗偱傕丄帋崌偱傕丄枴曽偺慖庤摨巑偱懅偯偐偄傗丄娋偺傎偲偽偟傝傗丄懱壏傪姶偠偁偭偰偄傞丅偙偺廗暼偑擔忢惗妶偵傕懕偒丄慖庤摨巑偑廤傑傟偽丄垾嶢偑傢傝偵僾儘儗僗媄偑斺業偝傟傞丅擭乆丄壜垽偄屻攜偑偱偒偰偄偔傛偆偵側傞偲丄Ng偺僾儘儗僗媄偵偼丄傑偡傑偡杹偒偑偐偐傝丄岾塣側旐奞幰偑懕弌偡傞丅堸傒夛偺惾偱偼丄戝惡偱偐傢偝傟傞儔僌價乕択媊偺側偐偵丄媄傪偐偗傞幰偲偐偗傜傟偨幰偺偆傔偒惡偑崿偞傞丅側傫偲傕寲憶偱偁傞丅偝偡偑偵丄愭攜楢拞偵偼偦偙傑偱巇妡偗偰偙側偄偑丄僌儗乕僪僨儞偑偠傖傟偰偔傞傛偆偵丄懱偛偲傇偮偐偭偰偁偄偝偮偵偔傞偺偱丄桘抐偼側傜側偄丅傕偭偲傕丄偦傟偑側偵傛傝偺垽忣昞尰側偺偩丅偲傔傞傢偗偵傕偄偔傑偄丅
偁傟偼丄2晹儕乕僌偱偺桪彑傪寛傔丄偟偐偟巆擮側偑傜擖懼愴傪僪儘乕偱廔傢傝丄1晹傊偺徃奿偵偼帄傜側偐偭偨僔乕僘儞偩偭偨丅傢偨偟偵偲偭偰偼丄偦傟偑尰栶岞幃愴丄嵟屻偺堦愴偩偭偨丅僲乕僒僀僪偺揓偑柭傝丄Ng偼偟偽傜偔僌儔儞僪偵嵗傝崬傫偱摦偐側偐偭偨丅傢偨偟偼丄僑乕儖億僗僩偺榚偵偹偦傋偭偰丄拡傪挱傔偨丅傗偗偵偺偳偐側搤偺嬻偩偭偨丅
夨偟偄偑丄棃婜偵偮側偑傞偩偗偺偙偲偼偟偨丅嵞婲傪惥偭偰丄僆僼偵擖偭偨丅Ng偼嶥杫偵婣嫿偟偨丅偦偟偰丄偦偺斢丄揻寣偟偰昦堾偵偐偮偓偙傑傟偨丅懄丄擖堾丅偦傟偐傜丄堦搙傕戅堾偡傞偙偲側偔丄敿擭傕宱偨側偄偱惱偭偨丅
惡側偒媽桭偲偺嵞夛偼丄晄巚媍偵惷鎹偩偭偨丅
嵼嫿傊偺掕廧傪弨旛偡傞偨傔偺廐揷朘栤偺婜娫傪棙梡偟丄嵢偲傆偨傝偱丄嶥杫傑偱懌傪怢偽偟偰丄慄崄傪偁偘偝偣偄偨偩偄偨丅摉帪偺儊儞僶乕偼丄傛偔傢偑壠偵攽傝崬傒偱梀傃偵偒偨丅Ng傕偦偺傂偲傝偱丄嵢傕掜偺傛偆偵壜垽偑偭偰偄偨丅
偛曣摪偼丄偄傑傕尦婥偱偍傜傟傞丅巚偄弌榖偟偵恠偒傞偙偲偑側偄丅
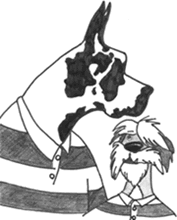 梒彮偺偙傠偺偙偲丅拠偑椙偔丄偄偮傕孼偺屻傪偮偄偰偁傞偄偰偄偨擔偺偙偲丅傗偑偰傆偨傝偲傕儔僌價乕偺悽奅偵峴偒丄儔僀償傽儖憟偄偲側偭偨偙偲丅傗偼傝娻偱惱偭偨晝恊偺偙偲丅撧椙偺崅峑偵儔僌價乕棷妛偝偣偨偑丄偨偩傂偲偙偲傕媰偒偺揹榖傪擖傟偰偙側偐偭偨偙偲丅崅峑搶惣懳峈偵慖敳偝傟偨婌傃丅偦傟偑戝妛偐傜偺僗僇僂僩偵偮側偑傝丄幮夛恖傑偱儔僌價乕傪懕偗傞偒偭偐偗偵側偭偨偙偲丅偦傟偑側偗傟偽丄嶥杫偱曣巕偱怘摪傪宱塩偟偰偄偨偐傕抦傟側偄偙偲丅丒丒丒丒丒
梒彮偺偙傠偺偙偲丅拠偑椙偔丄偄偮傕孼偺屻傪偮偄偰偁傞偄偰偄偨擔偺偙偲丅傗偑偰傆偨傝偲傕儔僌價乕偺悽奅偵峴偒丄儔僀償傽儖憟偄偲側偭偨偙偲丅傗偼傝娻偱惱偭偨晝恊偺偙偲丅撧椙偺崅峑偵儔僌價乕棷妛偝偣偨偑丄偨偩傂偲偙偲傕媰偒偺揹榖傪擖傟偰偙側偐偭偨偙偲丅崅峑搶惣懳峈偵慖敳偝傟偨婌傃丅偦傟偑戝妛偐傜偺僗僇僂僩偵偮側偑傝丄幮夛恖傑偱儔僌價乕傪懕偗傞偒偭偐偗偵側偭偨偙偲丅偦傟偑側偗傟偽丄嶥杫偱曣巕偱怘摪傪宱塩偟偰偄偨偐傕抦傟側偄偙偲丅丒丒丒丒丒
偄傑偼汷攌偵偼嫃側偄屘恖偺榖偟傪偟偰偄傞偲丄偦偺斵偑摉帪偺傑傑偵偦偙偵嵗偭偰偄傞偐偺傛偆側嶖妎傪妎偊傞丅傢偨偟偨偪偺榖偟傪丄側偵傕尵傢偢丄栙偭偰傢傜偭偰暦偄偰偄傞丅偄傑斵偼丄偛曣摪偲傢偨偟偲嵢偺怱偵廻偭偰偍傝丄傢偨偟偨偪偺側偐偵丄酳偭偰丄偝傑偞傑偵昞忣傪傒偣偰偄傞丅
偦偆偄偆偙偲傪丄傢偨偟偨偪偺朘栤偵傛偭偰丄偛曣摪偵傕姶偠偰偄偨偩偄偨偺側傜偽丄婐偟偄尷傝偩丅傢偨偟偺曣偲摨擭戙偱偁傞偐傜丄偡偙偟恊岶峴傪偟偰偁偘傜傟偨傛偆側婥暘偵側傞丅
2帪娫傎偳傕榖偟偙傫偩偑恠偒傞偙偲偑側偄丅偁偭偲偄偆娫偵婣傝偺僼儔僀僩偺帪娫偑敆偭偰偒偰偟傑偭偨丅柤巆傝偼恠偒側偄偑丄傑偨偺嵞夛傪惥偭偰丄偍偄偲傑偡傞偙偲偵偟偨丅
偙偺擔偺嶥杫偼丄壐傗偐側擔傛傝偩偭偨丅尒憲傝傪庴偗側偑傜丄儗儞僞僇乕偵忔傝崬傕偆偲偡傞偲丄偵傢偐偵戝晽偑悂偔丅攚拞傪僪儞偲墴偝傟偨婥偑偟偨丅傆傝傓偔偲丄僌儗乕僩僨儞偑晽偵側偭偰偠傖傟偮偄偰偒偨丄偦偆巚偭偨丅
