








<2006.6.10初稿>
かつて横浜市の南区に住んだ。妻がはじめての赤ん坊を身籠ったことで勤めを辞め、それを機会に社宅に引っ越した。
一棟建てだけの3階屋に12所帯があり、間取りが六畳ニ間に、同じく六畳のダイニングキッチンとバス・トイレという、40㎡あまりのまことにこじんまりとした社宅だった。入居時は、夫婦ふたりだったが、やがて五人家族となった頃には、一間に布団を寸分の隙間もなくビシリと敷き詰めて寝起きした。反して庭は、ブランコや藤棚があり、ちびっこ野球やサッカーもできるほど広大だったし、フェンスをひと越えした竹やぶで、子どもたちは筍を掘ったり、秘密基地を造ったりしていた。
12所帯だけということもあってか、現代版の長屋のような雰囲気があった。若夫婦がほとんどで、子どもたちも同世代であり、みな、仲が良かった。夏場など、ときおり夕涼みと称して、奥様連中でゴザを敷いて宴会が始まる。旦那陣が、会社から帰ってくる頃には、すっかり盛り上がっており、ちょいとにいさん寄ってらっしゃいよ、と言いながら、無邪気にケタケタ笑っていた。男性陣も三々五々輪に加わり、しまいには社宅を上げた大宴会になった。そんなこともあった。
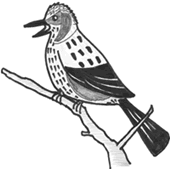 社宅は、かなり急な坂道を登りきった先に建っていた。わたしたちの部屋が3階にあったこともあり、晴れ渡った日に遠く富士を臨む眺めは絶妙だった。空や雲の移り模様というのは、子どもの目にも面白いのだろう。窓辺に椅子を引き寄せて、じっと見入っているときがある。
社宅は、かなり急な坂道を登りきった先に建っていた。わたしたちの部屋が3階にあったこともあり、晴れ渡った日に遠く富士を臨む眺めは絶妙だった。空や雲の移り模様というのは、子どもの目にも面白いのだろう。窓辺に椅子を引き寄せて、じっと見入っているときがある。
おとうさん、おかあさん、みて、おそらがふたつあるよ、と指を差す。
視線を指の先に移すと、暮れなずむ夏の夕日に、地平線が深紅に燃えて、赤富士が映えている。しかし、上の空には夜が迫り、もう一番星が煌いている。
あかいそら、とあおいそら。たしかにふたつの空がある。
狭い家屋にあって、家族がぴたりと肌温度で寄り添いながら、外部にその密集感を解放できる自然空間がある、そういう、子育て時期の理想的な環境があったのではないかと思う。
はて、前置きがながくなってしまった。
この社宅の庭先におおきな欅(けやき)の木があった。
春には、鳥が巣をつくり、卵を産んで、雛を育てた。おおきな欅だったから、巣の収容能力も高かったのだろう、巣から落ちてしまった雛をみつけることがときおりあった。メジロやヒワやシジュウカラ、・・・。みつけるのは朝の掃除当番さんや始終、外で遊んでいる子どもたちだ。カラスや青大将にやられずに幸いだった。そして、それを拾っては決まって我が家に持ち込んだ。
‘ふんご’という藁籠で落ち着かせ、種類を見分けて、食性や生育日数にあった餌を調合して与えなければならない。わたしは、小さいころから平野や山の野鳥を何十羽と育ててきた。巣落ちした雛から育てた経験もたくさんある。はじめ、ガキ大将格の小学生が拾ってきたメジロを無事育てて、やがて野に還した。彼には、それが鮮烈な驚きだったらしい。以来、ガキ大将はわたしを畏敬のまなざしでみつめるようになり、彼の子分らもそれに倣った。どうやら、トリハカセと呼ばれていたらしい。コウエイなことである。
ある日、子どもたちは大物を見つけた。両手にあまるほど大きく、グロテスクである。しかし、どうもカラスではなさそうである。すわ、これはトリハカセだ、ということになったのだろう、早々に持ち込まれた。
見ると、ヒヨドリの雛であった。
しかも、巣立ち前の状態まで生育している。ここまで育つと限りなく野性の生態に合わせた環境なり、餌を用意しないといけない。つまり、果実や蝉などの昆虫を食欲旺盛な雛に合わせて、給餌しなければならない。弱ったな、と思ったとたん、持ち込んだ子どもたちの真剣な視線にぶつかった。まかせとけ、と胸をドンと叩いて、これはヒヨドリという鳥でね、とひとしきり説明し、菓子を持たせて帰した。
どうしようかとしばらく思案したが、やはり手はひとつしかない。
鳥かごを組み立て、正面を除いて、黒いきれで覆う。床に古新聞を敷いて、入り口を5㎝ほどあけ、そのままの状態でベランダに置いた。親鳥が、このかごに雛が入っているのを見つけ出して、餌を運んでくることを期待したのである。このベランダは、親鳥のテリトリーの範囲内にある。
果たして、ねらいはずばり適中した。ものの数分も経たないうちに、母鳥が様子をうかがいにやってきた。ベランダの周りの木枝から呼びかけている。どうも、そとに連れ出そうとしているらしいが、それには入り口が狭すぎる。やがて、意を決したように餌を運び始めた。果実、昆虫、果実、昆虫、果実・・・と、栄養のバランスをとるかのように順に採餌している。鳥かごの前にたって、数㎝の隙間から雛の口まで餌を押し入れる。このベランダという空間が、怖い人間の生活圏にあることは、母鳥もじゅうぶん承知しているだろう。ときおり、左右の様子を警戒しては、それでも熱心に給餌を繰り返す姿は感動的ですらあった。
その日からしばらくは日の出とともに早起きをした。暗くなってから、保温も兼ねて、布で覆いかぶせ、室内に移動した鳥かごを、またベランダに出すためである。早起きをした、というよりも、早起きさせられた。日の出とともに、母鳥がベランダにやってきては、おはよう、おはようございます、わたしの息子をはやくベランダに出してやってくださいまし、とばかり、ひーよひーよ啼くのである。
ガキ大将とその子分らは、まいにち我が家にやってきて、ガラス窓越しに、そっと息を殺して、この母鳥と雛とのやりとりを観察した。いつも輝いている彼らの目が、いっそうキラキラしていた。
一週間ほど経った。そろそろ頃合いだ。産毛はすっかりなくなり、持ち込まれたときよりもひとまわり大きく成長した。その日の朝、いつものようにベランダに鳥かごを出したが、入り口を全開にした。朝は、なんどか餌をやりとりしている声が聞こえていたが、やがて静かになった。どうやら無事に巣立ったようだ。
やれやれ、これで子どもたちへの面目も保ったかなあなどと思いながら、鳥かごやベランダを清掃していると、その片隅に、新しい蝉の死骸がひとつ転がっている。
これはまことにつまらぬものですが、このたびは息子がたいへんお世話になりました、とばかりに母親が置いていったもののように想えた。苦笑いしながら捨てようとして、しかし手をとめた。そうだ、ガキ大将たちにこのお土産は見せてあげなくてはならない、そう思えたのだった。
