








<2008.1.22>
かつて、丹頂鶴を追って、厳冬の釧路湿原にかよっていたことがある。ひと冬に数回を5年ほども続けただろうか。いまは個体数も900羽以上に増え、サンクチュアリなどの設備も随分整ったが、当時の生息数は1/3だったし、餌場にも粗末なほったて小屋がぽつんと建っているだけだった。
風連湖の白鳥の撮影ついでに寄ってみたのがきっかけとなる。白鳥は所作は直線的だが、鶴には曲線美がある。綺麗だな、とは思ったが、まさか通うようになるとは、そのときは考えていなかった。
翌冬の初めに夢を見た。
紺碧の空のはるかかなたから、なにものかが、らせん状にゆったりと降りてくる。
目を凝らしてみると、それは何百何千というおびただしい鶴の群れだ。しだいしだいに大きくなって、あたかも天女のように・・・。そこで目が醒めまして、鶴が俺を呼んでいる!となった。
貧乏サラリーマンだったので、カメラの機材も十分ではなく、超望遠レンズには手が届かない。となると、なるべく鳥に近づくしかなくなる。したがって、採餌場に飛んでくる鶴を待ち受けるのではなくて、湿原の中に入り込んで、地形や葦の群生に身を隠して撮影することになる。いまにして思うと褒められた手法ではないが、鶴の習性を体で感じなければ駄目で、自分自身が野生に戻る必要がある。秋田の田舎に育った小天狗には、うってつけというわけだ。
あるとき、雪裡川の川上で、鶴の夫婦が遠望された。求愛のダンスをしている。
背景の川や丘といい、鶴の仕草といい、申し分ない光景。ところが、途中に障害物がほとんどないので、近づこうとしても丸見えになってしまう。
こうなると残された選択肢はひとつしかない・・・匍匐(ほふく)前進。
実際には20分かそこらだったろうが、とても長い時間、はいつくばっていたような感覚だった。ようやく、50㍍ほどまで距離を詰めることができた。相変わらずオスはメスの周りを跳ね廻り、そこらに落ちている枝をくわえなげては、さかんに気を引こうとしている。
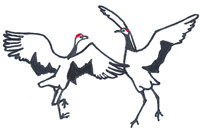 丹頂鶴の頭頂の赤さ。あれは羽毛ではなくて、血管である。だから、怒ったり、嬉しかったりすると興奮して真っ赤になり、範囲も広がる。求愛の最中だから、その朱色が雪原に灯るかのように映えている。
丹頂鶴の頭頂の赤さ。あれは羽毛ではなくて、血管である。だから、怒ったり、嬉しかったりすると興奮して真っ赤になり、範囲も広がる。求愛の最中だから、その朱色が雪原に灯るかのように映えている。
しめしめ、と背負っていたカメラにそろりと手を伸ばし、やおらレンズを向けようとした、その瞬間。
殺気を抑えられない未熟な剣士をあざわらうかのように、あれよという間に二羽は飛び去ってしまった。
ひとり残された青年は、もう笑うしかなかった。なぜか分からないが、アハハと心の底から笑えるのだった。
夕映えにねぐらに還る姿も、また実に風情があり、最後の一羽まで見届けて引き上げるのだが、そうなると、もうすっかり暗くなった夜道をトボトボ歩いて宿まで帰ることになる。街灯なぞ、もちろんないので、月明かりが頼り。ふと、見上げると満天の星。伸ばすと本当に手に届きそうに、おびただしい星々がちらちら瞬いている。じきにそれが滲んでくる。涙が溢れてくるのだ。悲しくもないのに、・・・。ああそうか、人間ってあんまり美しいものを見ると泣けちゃうんだ。キタキツネがおりよくコーンと鳴いたりして、なんだよドラマじゃあるまいに、とつぶやいた。
ほふくぜんしん物語には余話がある。
雪原にひとり残されたわたしは、鶴夫婦が踊っていた場所まで行ってみた。
すっかり凍りついた小さな泉がダンスのステージとなっていた。鶴の足跡は、人間の掌よりふた廻りくらいも大きい。それが、泉の新雪に沢山残っている。
レンズを広角に換え、ダンスのステップの名残を、凍てついた泉を、雪原を、吹き渡る風に揺らぐ葦を、そして冴え渡った空を撮った。
のちほど、この一枚が展覧会で入選した。
『見渡す限りなにもない真冬の湿原には、自然の苛酷で峻厳な美がある。しかし、目を落とすと、そこには鶴の夫婦がついさきほどまで行っていた交歓の徴しがある。たくましく息づく生命力を感じさせる』という批評が、とてもくすぐったかったのを昨日のように思い出す。
